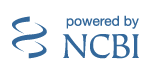拡張型心筋症 (Dilated Cardiomyopathy: DCM) は「 (1) 左室のびまん性収縮障害と (2) 左室拡大を特徴とする疾患群」と定義される (心筋症診療ガイドライン(2018年改訂版)による)。 診断の確定には、基礎疾患ないし全身性の異常に続発し類似した病態を示す「二次性心筋症」(WHO/ISFC の「特定心筋疾患」)を除外する必要がある。欧州心臓学会の分類でも、DCMは「左室拡大と左室収縮能障害を特徴とし、びまん性の収縮障害を引き起こし得る異常な負荷状況 (高血圧や弁膜症) 及び冠動脈疾患の合併がない疾患群」と定義されている。DCMの有病率を正確に記述した報告はないが、心不全患者の総数が全国で120万人に達するという推計において、軽症を含めたDCMの有病率は人口1,000人あたり0.5人程度と推定されている。我が国では、DCMが心臓移植の原因疾患として最も多い。
近年、DCMの病因は遺伝性と非遺伝性(慢性炎症や自己免疫を含む)に分けて分析されるようになり、特に成人発症のDCMの多くは両者が関与する症候群と考えられている。家族性DCMでは、既知の原因遺伝子変異が20-40%に検出され、多くは常染色体顕性遺伝形式を示すが常染色体潜性遺伝形式を示すものもある。
家族歴の乏しい患者でも遺伝子変異が見つかり、特定の患者に複数の変異が認められることも少なくない。
DCMに関してのみの予後に関する最新のデータは無く、平成11年の厚生省の調査では、本症の5年生存率は76%となっていたが、その後の治療法の進歩とともに改善していると考えられる。家族内発症による遺伝子変異の保有者や、不整脈のみで発症した早期DCMについて、収縮力がほぼ正常であっても注意深く経過観察し、早期診断に努めることが重要である。家族性DCM家系内では無症状症例の10~20%で5年以内にDCMに進展することも報告されている。
心不全に関しては心移植以外に根治的療法はない。うっ血や低心拍出の急性期心不全の症状があるときは、できるだけ安静にさせると共に食塩制限(5-8g) と水分制限が必要である。さらに左室収縮能障害 (駆出率の低下した心不全) に対しては、アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬、β 遮断薬を早期に用いる。心臓再同期療法 (ペースメーカーを使って心臓のポンプ機能を改善する方法) の予後改善効果も認められている。
重症心室性不整脈による突然死への対策が重要であり、植込型除細動器が二次予防として最も大きな役割を果たしている。DCMに失神が合併した場合には、植込型除細動器の適応となる。重症心室性不整脈が出現する場合には、副作用に注意しながらクラスIIIの抗不整脈薬アミオダロンを投与する。本症では、左室の拡大とびまん性壁運動低下から、左室腔に壁在血栓が生じる場合や、左房拡大を伴う心房細動例で心房内血栓が生じる場合もある。これらに対して、ワルファリン等による予防的な抗凝固療法を行う。
家族性DCMの40-50%は、30種類以上見つかっている原因遺伝子のいずれかの変異であると報告されている (J Am Coll Cardiol. 2011. PMID: 21492761)。DCMの10-20%はTTN遺伝子の短縮型変異に起因しているとされ (N Eng J Med. 2012. PMID: 22335739)、その他の遺伝子の家族性DCMに占める割合は、LMNAが6%、MYH7が4.2%、MYH6が3-4%、SCN5Aが2-4%、MYBPC3が2-4%、TNNT2が2.9%、BAG3が2.5%、ANKRD1が2.2%、RBM20が1.9%、TMPOが1.1%、LDB3が1%、TCAPが1%、VCLが1%、TPM1が<1-1.9%、ACTC1、CSRP3、DES、NEXN、PSEN1、SGCDがそれぞれ<1%との報告がある (J Am Coll Cardiol. 2011. PMID: 21492761, Nat Rev Cardiol. 2013. PMID: 23900355)。
現時点で、日本人DCMの原因遺伝子頻度解析に関する原著論文は見当たらないようである。