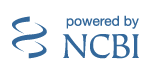結節性硬化症 (Tuberous Sclerosis Complex: TSC) は腫瘍抑制遺伝子のTSC1遺伝子とTSC2遺伝子のいずれか一方の変異により生じる常染色体優性遺伝性疾患であるが、約60%は孤発例で新生突然変異と考えられる。TSC1遺伝子とTSC2遺伝子の産生タンパクであるハマルチン (Hamartin) とチュベリン (Tuberin) はHamartin-Tuberin複合体を形成し、下流のmammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1)を制御することで細胞の増殖の制御をしている。TSCではmTORC1の脱抑制が起こり、上衣下巨細胞性星細胞腫 (SEGA)、腎血管筋脂肪腫、リンパ脈管筋腫症 (Lymphangioleiomyomatosis: LAM)、顔面の血管線維腫などの過誤腫を全身に生じる。また、Hamartin-Tuberin複合体の機能不全によって自閉症やてんかんなどの神経症状も生じる。TSCの診断には、2012年にワシントンDCで開催された第2回のTSC Clinical Consensus Conferenceで批准された新規診断基準を用いる。本診断基準では、まず遺伝学的検査を施行し、TSC1遺伝子またはTSC2遺伝子のいずれかに機能喪失型変異があれば確定診断に充分であるが、遺伝学的検査で変異が確定できなかった場合や検査を受けていない場合には臨床診断を用いる。ただし、TSCの患者で病的バリアントが検出できるのは、約75-90%であり、遺伝学的検査で必ずしも検出できるわけではない。
TSCの頻度は出生児5,800人のうち1人とされている。
障害と死亡の最大の原因は中枢神経系の腫瘍である。早期死亡の原因の第2位を腎疾患が占めている。腎腫瘍や肺LAMは重度になると生命予後に関係することが多い。いずれの症状に対しても現時点で根本的な治療法がないため、生涯にわたる加療が必要となる。
現在確立されている治療法は、ほとんどが対症療法である。てんかんに対しては抗てんかん薬や時に病巣の外科的切除が行われる。腎血管筋脂肪腫に対しては経動脈塞栓術 (TAE) や外科手術による切除、皮膚の腫瘍に対してはレーザー、液体窒素を用いた冷凍凝固術や外科手術を行う。脳腫瘍に対しては手術又は薬物療法 (mTORC1阻害剤)、腎腫瘍に対しては薬物療法 (mTORC1阻害剤)、カテーテル治療 (経動脈塞栓術) 又は手術が行われる。肺LAMに対してはホルモン療法などが試みられるが確立された治療法はない。
| Gene symbol | OMIM | SQM scoring* | Genomics England PanelApp | Phenotype | Variant information |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC1 | 191100 | TSC1 (AD) | https://omim.org/allelicVariants/605284 | ||
| TSC2 | 613254 | TSC2 (AD) | https://omim.org/allelicVariants/191092 | ||
| IFNG | 613254 | N/A | TSC2 angiomyolipomas, renal, modifier of ( AD ) | https://omim.org/allelicVariants/147570 |
TSCで、TSC1遺伝子の病的バリアントによるものは~26%、TSC2遺伝子によるものは~69%、原因不明が~5%である。 (GeneReviewsより引用)。
日本人TSC患者27人 (孤発例23人と家族例4人) においてTSC1とTSC2遺伝子のシークエンス解析を行ったところ、病的疑いのバリンアトをTSC1遺伝子に4つ、TSC2遺伝子に6つ認めたという報告があり (Am J Med Genet. 2000. PMID: 10607950)、同様に、日本人TSC患者38人 (孤発例25人、家族例11人と不明例2人) においてTSC1とTSC2遺伝子の変異解析を行ったところ、TSC1遺伝子に7つ (孤発例4人と家族例3人) とTSC2遺伝子に15つ (孤発例10人、家族例5人と不明例1人) の病的バリアントを認めたという報告がある
(J Hum Genet. 1999. PMID: 10570911)。